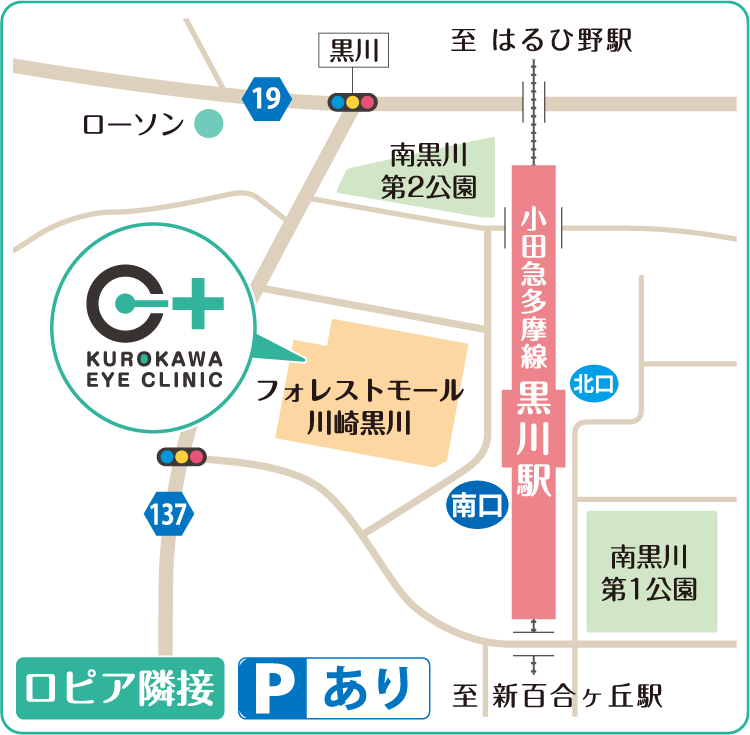小児眼科について
小児眼科では、文字通りお子様の眼に関する病気や症状を専門に診療します。私たちの視力は、最初から備わっているわけではありません。新生児の視力は、明かりがぼんやりとわかる程度です。その後、様々な視覚刺激を受けていき、徐々に視力が発達していきます。そして、8~10歳頃になると視力は完成し、大人と同じくらい見えるようになります。
小児眼科は、このように変化していくお子様の視力を、しっかりとサポートしていく役割を担っています。当院では、一般的な眼科疾患のみならず、視力に関する様々な相談も受け付けております。さらに、小児期の先天性疾患の検査や、必要に応じて専門施設へのご紹介も行っておりますので、お子様の目のことで、少しでも気になることが出てきましたら、お早めに受診するようにして下さい。
気になることがあれば早期受診を
視力が成長する過程で何らかの目のトラブルが起こることは少なくありません。しかし、お子様は目に異常を感じていても、それを言葉で表現できません。きちんと物が見えていなかったり、目に痛みがあったとしても、多くを語ってはくれないのです。したがって、周囲の大人の方が、お子様の目の異変に気付いてあげる必要があります。視力は生後3歳ごろから急速に発育します。その時期に何らかの原因で成長が途絶えると、将来的に弱視のリスクが高まるので、注意が必要です。
このような症状に気づいたらご相談を
- まぶたが開かない
- 目が揺れる
- 目の色がおかしい
- 涙の量が多く、いつも目が濡れている
- 目が内側に寄り過ぎている、外側を向いている
- テレビやおもちゃを極端に近づいて見ている
- よく眩しそうに眼を閉じる
- 目を細めて物を見ている
- 部屋の壁や出っ張りによくぶつかる
- フラッシュを焚いて写真を撮ると、片方の目だけ違う色に光っている
- 学校健診などで精密検査が必要と言われた など
小児眼科でよく見られる症状
斜視
弱視
仮性近視
お子様の目が成長する過程で、目軸の長さや水晶体の厚みを調整する毛様体筋の緊張などが原因となり、目の屈折率が一時的に変化し、焦点がうまく合わなくなることがあります。このような一過性の状態を「仮性近視」と呼びます。このようなときは、目の緊張を和らげる薬などを用い、通常は改善に向かうことができます。しかし、治療によっても裸眼視力が良くならず、これ以上の改善が見込めない段階に達したならば、眼鏡を処方いたします。
近視
子供たちの近視の増加は世界的な問題となっています。近視は遺伝的な要因と、環境的な要因両方によるものですが、近年の近視の爆発的な増加はこの環境的な要因によると考えられています。具体的には、屋外活動の減少、デジタル端末などの近見作業の増加、睡眠のとり方の変化などです。
まず眼鏡をしっかり合わせることが重要ですが、その他に病院でできる近視予防法としては、以下があります。(近視治療はすべて医療保険適応外です)
低濃度アトロピン点眼
- 効果
- 臨床試験で、2年間の使用により近視の進行を抑える効果が確認されています。
- 持続性
- 効果は最大で3年間持続すると報告されています。
- 安全性
- 高濃度アトロピンに比べ、副作用が少なく、日常生活への影響はほとんどありませんが、まれに明るい光をまぶしく感じることがあります。
治療の流れ
アトロピン点眼液を使用した治療は、完全予約制です。
治療開始後は、定期的にご来院いただき、近視の進行や目への影響をしっかりと見守りながら進めていきます。
-
初日
屈折値、視力、眼圧、眼軸長測など定を行い、医師が目の状態を確認します。点眼薬の使い方や注意点を詳しく説明し、同意書にご署名頂いたのち、1か月分の点眼薬を処方して治療開始します。
-
1か月後
検査、診察で効果や副作用の有無を確認し、問題なければ治療開始3か月後の検診までの点眼薬を処方します。
-
3か月毎
3か月毎の定期的な診察で、視力や眼軸長の変化を確認します。
次回の検診までの点眼薬を継続処方し、治療を進めます。