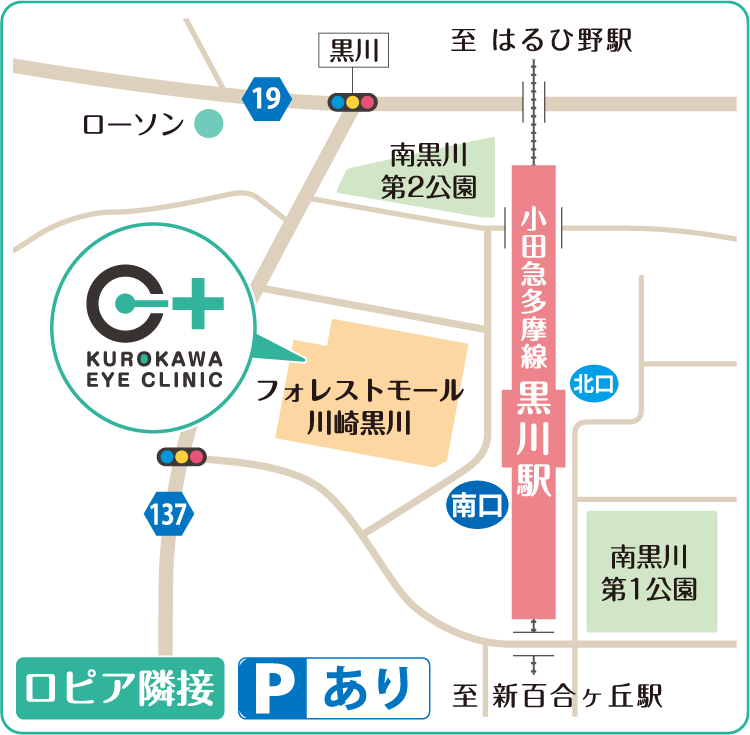一般眼科について
一般眼科は、目に関する様々なお悩みを抱えている患者様の治療を幅広く行う診療科です。物がかすんで見える、視力が低下する、目が充血する、目の奥が痛むといった問題が生じると、日常生活に大きな影響が出ます。この中には、しばらく安静に過ごすことで解決する疾患もありますが、早期に治療を行わないと失明の危険がある疾患もあります。
この地域のかかりつけ医です
当院では、日本専門医機構認定眼科専門医である院長が中心となり、様々な眼の病気の診療を行っていきます。地域の皆様のかかりつけ医として、眼科領域における地域の皆さまのかかりつけ医、眼のホームドクターとしてお役に立てる存在でありたいと考えています。下表のような症状がみられるときは、お気軽に当院をご受診下さい。
このような症状の方はご受診を
- 目が疲れやすくなった
- 景色がぼやけて見える
- 目の中に異物感がある
- 目がゴロゴロする
- 目がかゆい
- 黒目が白っぽい
- 慢性的に目がしょぼしょぼする
- 目が乾燥する(ドライアイ)
- 目が充血している
- 目ヤニや涙がよく出る
- まぶた全体が赤く腫れている
- 肩こりや倦怠感がある
- 頭痛やめまい、吐き気がある など
早期発見・早期治療が重要
目の病気の多くは、ほとんど自覚症状が見られないまま病状が悪化していきます。そして、気がついたときは視力が大きく低下していたり、視野が狭くなったりして、治療が難しくなるケースが少なくないのです。このような状況にならないためには、病状が進行する前の早い時期に受診し、治療を開始することが重要です。早期発見・早期治療によって眼の機能の悪化を食い止められる可能性が高まります。目の病気によって仕事や学業、日常生活などに支障をきたすことがないよう、目の見え方の異常・違和感を覚えた際は、お早めに当院までご相談下さい。
主な眼科疾患
白内障
緑内障
眼瞼下垂
ドライアイ
角膜炎
糖尿病網膜症
加齢黄斑変性
花粉症
花粉症とは、花粉がアレルゲンとなってアレルギー症状を引き起こしてしまう病気です。アレルゲンとなる花粉については、スギやヒノキが有名ですが、そのほかにも、シラカバ、カモガヤ、ヨモギ、ブタクサなど非常に多くの種類があります。これらの花粉のなかには、秋の季節に飛散するものもあるので、秋に限定してアレルギー症状が出現することもあります。
主な症状
花粉症による主な症状ですが、多くの場合、目のかゆみや痛み、異物感に悩まされます。目が充血したり、涙が止まらなくなる患者様もいらっしゃいます。まぶたやまぶたの裏側が腫れてしまい、気分が優れなくなることもあります。目の症状だけでなく、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状もみられます。病気が悪化すると、咳、皮膚のかゆみ、頭痛といった症状にも悩まされます。
花粉症の治療
花粉症の治療に先立ち、まずは日常生活での注意点があります。花粉が飛散している時期に外出するときは、眼鏡やマスクを装着し、花粉が体内に入り込まないようにします。帰宅時は、衣服や顔などに付着した花粉を洗い流すため、シャワーを浴びることも大切です。こうした対策に加え、薬物療法を行います。基本的には抗アレルギー点眼薬を使用することにより、症状を緩和させます。花粉の飛散が始まる2週間ほど前から、シーズン終了まで継続することが症状緩和に有用といわれています。症状の重症度に応じて、副作用に注意してステロイド点眼を併用する場合もあります。
結膜炎
結膜炎は、様々な原因によって白目を覆っている膜が炎症を起こしてしまう病気です。スギやヒノキなどの花粉、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛や糞などが原因となるアレルギー性結膜炎、目の周囲に存在している細菌が原因となる細菌性結膜炎、ウイルスが原因となるウイルス性結膜炎などがあります。涙や目やにが多くなった、眼が充血している、瞼がはれぼったい、眼が痒い、痛いなどの症状がみられるときは、結膜炎の可能性があります。
結膜炎の治療
結膜炎の治療は、主にお薬を使って症状を改善させます。例えばアレルギー性結膜炎ならば、抗アレルギー薬をはじめとした薬物療法が主体となります。それでも症状が治まらずに日常生活や仕事に差し支える場合は、抗アレルギー薬を内服することもあります。重症のアレルギー性結膜炎である春季カタルの場合は、免疫抑制薬の点眼を検討します。また、細菌性結膜炎の場合は、抗菌薬の点眼などを使用します。ウイルス性結膜炎の場合は抗炎症作用の点眼等で対応します。アデノウイルスによる結膜炎である流行性結膜炎(はやり眼)の場合は生活指導なども重要になりますので、その都度ご説明させていただきます。また、はやり眼の合併症として角膜上皮下混濁という状態となった場合は、点眼加療が長期間に及ぶこともあります。
ものもらい
ものもらいは、まつ毛の毛根やその付近に黄色ブドウ球菌などの細菌が感染してしまい、そこに膿が溜まってしまう目の病気です。患者様によっては、まぶたに赤み、腫れ、痛みなどが現れるようになり、見た目にも影響が出ることがあります。なお、この病気の正式名称は「麦粒腫」となります。まぶたにできものができて痛いなどの症状がみられるときは、ものもらいの可能性があります。
ものもらいの種類
ものもらいは、感染が起きている部位によって「外麦粒腫」と「内麦粒腫」に分けられます。このうち外麦粒腫は、まつ毛付近でまぶたの皮膚面にあるツァイス腺やモル腺に細菌が感染することで発症します。まぶたの皮膚面に発赤や腫れが現れ、その中心部分には白い点がみられます。一方、後者の内麦粒腫は、まぶたの裏側にあるマイボーム腺に細菌が感染することで引き起こされます。この場合は、まぶたの裏側に白い点がみられるだけでなく、充血や腫れも起こります。
ものもらいの治療
ものもらいが比較的に軽度のときは、目を清潔に保つことで徐々に回復します。しかし、痛みや腫れ、目ヤニなどの症状があるときは、薬物療法が必要になります。患者様にもよりますが、抗生物質が含まれている目薬や内服薬を使用することにより、3~10日ほどで治癒します。膿が溜まっているときは、患部を少しだけ切開し、膿を排出させることもあります。
霰粒腫
霰粒腫(さんりゅうしゅ)とは、瞼の内側に存在するマイボーム腺と呼ばれる部位に肉芽腫というしこりができる病気です。霰粒腫は無菌性の炎症が原因となるので、典型的には痛みを伴いませんが、感染などを伴うと痛みを伴う”急性霰粒腫“という状態になります。小児から成人まで広く一般的にみられるものですが、高齢の方に出現してきた場合は悪性腫瘍である場合が稀にあり、注意が必要です。
霰粒腫の原因
まつ毛の付け根付近にあるマイボーム腺の出口がつまり、慢性的な炎症が生じることで肉芽腫という塊ができます。
霰粒腫の治療
小さいものであれば、数週間程度で自然に内容物が排出されたりすることがありますが、基本的にはしこりが小さくなることを期待して点眼や軟膏で炎症を抑えていきます。ただし、大きいものや再発するものでは点眼や軟膏の効果が限定的であることも多く、しこりの部分に薬を注射したり、手術で内容物を取り出したりします。また、前述のように瞼の悪性腫瘍が疑われる場合は、専門施設での手術が必要となります。
また、細菌感染を併発した場合、痛みや腫れの悪化などの炎症所見を伴うため、抗菌薬や痛み止めを併用しながら炎症を落ち着かせていきます。
マイボーム線機能障害(MGD)
マイボーム腺機能不全とは、瞼の内側にある“マイボーム腺”という脂の腺の機能が異常である状態です。この線から涙液中に出た脂は、瞼と眼の摩擦を防いだり、涙の蒸発を防いだり、涙液成分を安定化させたりする、眼表面の環境にとって重要なものです。
そのため、これらの機能が低下すると、「眼がしぱしぱする」「ごろごろする、痛い」「圧迫感がある」「乾く感じ」といった症状を起こしてしまいます。
マイボーム線機能障害の原因
MGDは“分泌減少型”と“分泌増加型”に大きく分けられますが、分泌減少型が圧倒的に多く、マイボーム腺からの脂質の分泌量が減るためにドライアイの原因となります。
分泌減少型には閉塞性、萎縮性、先天性があり、最も多いのが閉塞性です。加齢などでマイボーム腺内にごみが詰まってしまい、脂がだせなくなってしまいます。また、アトピー性皮膚炎などの病気が原因で起こるものもあります。
マイボーム線機能障害の治療
MGDの治療として、当院ではマイボーム線の圧迫(マイバム圧出)、抗菌薬の点眼・内服などを行っています。また、MGDではホームケアが重要となるため、アイシャンプーなどを用いたクリーニング法、温罨法や眼瞼清拭などの家庭でのセルフケア法を指導させていただきます。当院医師はLIME研究会というMGDの研究会に属しておりますので、治療法等について日々新しい情報を入手し、患者様に還元してまいります。