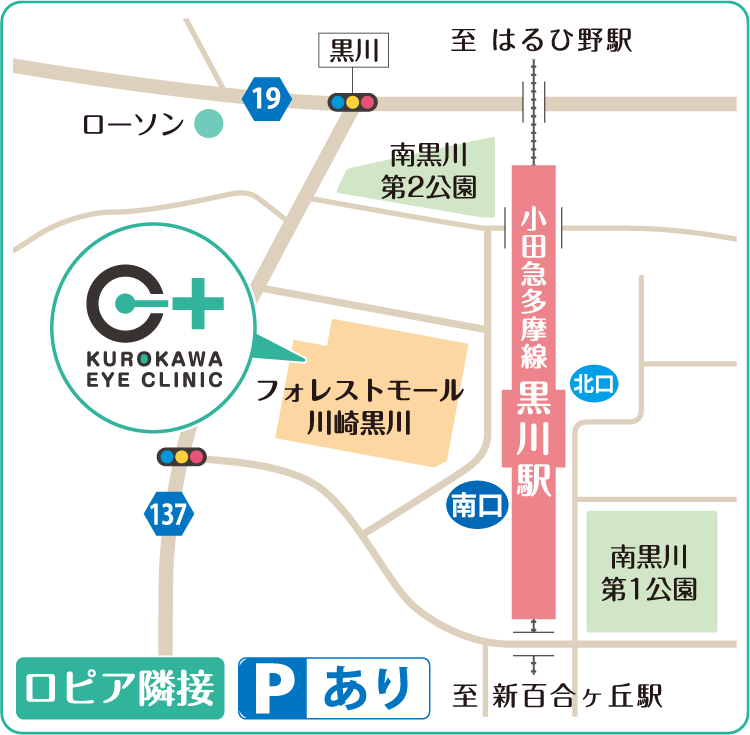糖尿病について
糖尿病は、血糖を細胞に取り込むインスリンというホルモンが十分に作用しないため、血液中のブドウ糖濃度が慢性的に高い状態になることで血管が傷つき、全身のさまざまな臓器が障害される病気です。この中には、自己免疫の異常などでインスリンが十分に分泌できなくなる「1型糖尿病」、生活習慣が原因で分泌されたインスリンの効きが悪い、もしくは分泌量が不足する「2型糖尿病」などのタイプがあります。
糖尿病網膜症とは
糖尿病網膜症は糖尿病の3大合併症の一つで、日本での成人の失明原因の3位と言われています。
網膜は眼底にある薄い神経の膜で、カメラで例えるとフィルムにあたる部分です。網膜にはものを見るための神経細胞が敷きつめられ、微細な血管が張り巡らされています。血糖が高い状態が続くと、それらの血管は少しずつ損傷を受け、変形したり、つまったりします。血管がつまると網膜の神経細胞に酸素が行き渡らなくなり、網膜が酸欠状態(=網膜虚血)となります。酸欠状態の細胞は酸素を得るため、血管を生やそうと、血管内皮増殖因子(VEGF)という物質を眼内にまき散らします。このVEGFにより、もろく崩れやすい異常な血管(新生血管)が形成されます。新生血管は機能に乏しいばかりか、自然にすぐに壊れ、眼内に出血をきたします。また、次第に網膜にかさぶたのような膜(増殖組織)が張ることで網膜剥離をきたしたり、本来血管のない部分に新生血管ができることで眼の中の水(房水)が排出できず、眼圧が上がり視神経が不可逆的に障害される血管新生緑内障などといった、失明に直結する合併症をきたしてきます。
糖尿病網膜症は末期になるまで自覚症状がない場合も多く、見えるから大丈夫という自己判断は危険です。糖尿病の人は目の症状がなくても定期的に眼科を受診し、眼底検査を受けるようにしましょう。
このような症状の方はご来院を
- 視界がかすんで見える
- 視野の一部分が欠けている
- 目の前をホコリのようなものがチラつく
- 目の前にカーテンがかけられたように黒く見える
- 目の奥の方が痛い
- 視力が急激に低下してきた など
糖尿病網膜症の治療
糖尿病網膜症の治療は、患者様の病気の段階などを考慮して行います。比較的に初期の「単純網膜症」と言われる段階ならば、糖尿病自体の治療が主体となります。食事や運動等の生活習慣の改善や血糖降下薬などの薬物治療を行っていきます。そして月1回は目の検査をし、状態を確認します。
糖尿病網膜症がある程度進行し、「増殖前網膜症」と呼ばれる段階になったときは、網膜光凝固術を行います。これはレーザー光線を虚血部位の網膜細胞にあてることで、新生血管の発生を予防したり、すでに出現してしまった新生血管を減らしたりすることを目的として行います。網膜症の進行具合によって、レーザーの照射数や照射範囲が異なります。網膜光凝固術は早い時期であればかなり有効で、将来の失明予防のために大切な治療ですが、見え方を改善したり、網膜の状態を改善させるものではありません(そういった治療は現状では存在しません)
さらに進行し、「増殖網膜症」と呼ばれる段階になったときは、様々な治療によって失明のリスクを減らす努力をします。出血や網膜剥離まで起こすと、専門施設での手術が必要です。
糖尿病黄斑浮腫とは
高血糖の状態が続くと、網膜の血管がもろくなったり、つまったり、炎症が起こったりして、血液が運ばれなくなったり、血管外に血液成分が漏れ出てしまうようになります。これらの結果、黄斑にむくみが生じたのが糖尿病黄斑浮腫です。黄斑は、ものを見るときに重要な働きをしているため、かすみ目や見え方の歪みが出現したり、進行すると視力の低下や失明に至ることもあります。
糖尿病黄斑浮腫の治療
糖尿病黄斑浮腫では、網膜の血流障害や炎症のために、“血管内皮増殖因子(VEGF)“という物質が眼内に放出されています。この物質が、血管から血液の成分を漏れ出しやすくしたり、脆く崩れやすい異常な血管を産生させたりすることで病気が発症、進行します。このため、VEGFを抑える薬(抗VEGF薬)を定期的に眼内に注射することで、黄斑浮腫の改善を図ることができます。